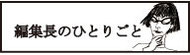セラフィーヌの庭

久々に、良い映画に出会いました。フランス・ベルギーの合作映画です。実在の女流画家セラフィーヌ・ルイの壮絶な人生の40代後半から晩年までを描いた物語です。
1912年、パリ郊外サンリスという村で家政婦をしながら、つつましく生きるセラフィーヌ。子供も夫もいない、天涯孤独である。彼女にあるのは絵を描くという密かな喜びだけ。そんな彼女の雇い主の別宅に、ドイツ画商ヴィルヘルム・ウーデとその妹が、夏の休暇を過ごすためにやってきた。彼は、あのアンリ・ルソーを見いだし、ピカソを誰よりも早く評価した、本物を見抜く鋭い審美眼をもった名プロデューサーである。彼女は家政婦として、彼の身のまわりの世話をすることになる。
ある日、ヴィルヘルムは偶然にも、彼女の描いた小さな作品を眼にする。そして、その奔放な構図、独自の色彩感覚に衝撃を受ける。「セラフィーヌ! 君には素晴らしい才能がある!」。 彼は彼女の作品の中に、今まで出会ったことのない激しさと、狂おしさと、大地の力強さを見たのだ。その矢先、第一次世界大戦が勃発。ドイツ人であるヴィルヘルムは、急遽、この地から撤収しなければならなくなる。
そして、再びセラフィーヌがヴィルヘルムに出会えるまでの時間は、長くて重い。セラフィーヌは、唯一の理解者を突然失い悲嘆にくれていた。しかし、ヴィルヘルムの言葉を信じて、孤独と貧しさの中で、絵を描く情熱を燃やし続ける。身を削って、大作を何枚も仕上げていく。昼は家政婦としてひたすら働き、野に咲く草花や小川の泥から絵の具を作り、創作活動はロウソクを何本も灯して、そのうす灯りの下で深夜まで続けられた。彼女の胸には、天から声が聴こえてくる。今、何を描くべきなのか。それをひたすら、キャンバスに定着させていったのだ。
このセラフィーヌを演じたヨランド・モローの演技力は秀逸である。彼女は観客に、セラフィーヌを女優が演じているということを忘れさせてしまう。そして、脚本も担当している監督マーティン・ブロボストの演出もまた素晴らしい。彼らには、感情移入させるための壮大な音楽など無用だ。セラフィーヌが草を踏んで歩く足音、鳥の声、水のせせらぎ、風に乗って運ばれてくるわずかな湿度、かぐわしい草花の匂い、春のうららかな陽ざし。そして、セラフィーヌは木々に触れ、風と対話する。彼女にとって、自然こそ何よりも愛しい最高の友であり、家族であることを、あれほどまでに、表現できるとは。ただただ、魅了させられるばかりである。
セラフィーヌを語るのに、象徴的なシーンがある。ある日、別荘の自室でヴィルヘルムが泣いているのを彼女は偶然見てしまう。その時、彼女が彼に言った言葉は、「悲しい時は野に出て、木々に触る。そして、草花や動物と話をすると良いですよ。悲しみなんか、すぐに消えていきます」
詳しい内容を説明しきれないので、セラフィーヌとヴィルヘルムの間に、男女の感情があったのではないかと早とちりしてしまう人がいるかもしれない。少なくとも、この映画の中では、それは違う。それより、既成概念の性など何の意味もなさない、ということに気づかされるのだ。
最後に。
普通、女性の人生は女であり、妻であり、母であり、そして、一人の人間である。それゆえ、何通りもの生き方をよぎなくされ、集中力を分散せざるを得ない、まして、母になった瞬間から無垢に生きることなど許されない。それに比べると、セラフィーヌは、最後まで無垢に、イノセントに生ききった女性である。同じ女性として、ある意味うらやましくもある。セザール賞主要7部門を独占しただけはある秀作である。