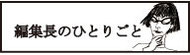墨いろの日々 歌の日々/五行歌(第一章) 書家・西垣一川
五行歌という詩歌。決まりは五行で書く。俳句や短歌のように文字数の決まりは無し。自分のリズムで感じたままを。季語も要らない。文語は避けるというくらいでしょうか。たったこれくらいの決まり。この新しい文芸がわたくしにはぴったり合っていた。短い詩を作るような五行で詠むという行為は心を鎮め、自分の生き方や発見を映し出す作業でもあった。
そして、五行歌のテーマを「愛」「自然」「書」と定め17年が過ぎた。ここでは、拙著、一川五行歌集『透理』(市井社)からも少しずつアップして言葉を添えたいと思う。

齢=よわい
曲み=たわみ
齢を重ねた
曲みを
美しいと思う
おとこの背も
おんなの乳房も
ある時、大好きな岸恵子氏の乳房を想像していました。彼女のにじみでるような美しさは老いてますます輝きを放っていていったい、女のわたくしでも魅力的なこの方の乳房はどのような乳房であろうかと想像した。
それは少し、林檎のような張りを忘れかけて軽い。乳首はもう若い頃の色素は消え、乳輪の色に近づき、柔らかく優しく垂れている。きっとその乳房は長い間、誰にも触れられず清く生きてきたのだろうと想像した。
男の背中は語ると申しますが、我が夫の背中は読書のせいで少し丸みを帯びてそのなだらかな曲線をわたくしは愛しい、美しいと感じる。ここでは年を重ね精神が深まったひとの表側の景色として感じた気持ちを美しいと詠んでみた。

種蒔く人は
地に
星を
散りばめる人
宮澤賢治を大好きだった父は学生のころから彼の本を蒐集していた。その影響もあってか食にこだわりのある父は勤めを辞めてからは自宅用に鶏を飼い、無農薬野菜を作るようになった。実家に戻るときはいつもデザートまでのコースが待っていた。決してオシャレなフレンチのようなものではなく旬の野菜で作った簡単なものであったが滋味深い「野菜」そのものが味わえた。父が亡くなった今では、その味が懐かしい。
同じころ種を蒔く父を思い「指先から・金色の・種子が・落とされる・光る大地」という歌を詠んだ。わたしには崇高な景色のように思えた。そして、そのひと粒ひと粒はきらきらとした星のようにも見えた。全ての種蒔く人々に感謝を込めて。

泰然とした
骨があり
それを包む
墨の潤い
というもの
骨格がきっちりと整いあとは自由。そういう書が理想である。そうでない書はどことなく不安感を残して見ていて後味が悪い。体内に純粋な日本の血が流れ、今、蠢いている血液、そのスピードは時速何キロで流れているのか。
生きている、生きていると思う。そんな自分から生命の息吹を墨で迸り出させる行為は、「たった今の自分」「ぴかぴかの自分」を紙に落とすことでもある。健康でも不健康でもその書が自分であり、鏡である。書けないことも多い。
しかし、どことなくこの歌に詠んだ「潤い」のある書に仕上がったとき、少し満足してお茶の時間にする。
文字の骨格、書の余白、墨の色、滲みなどを眺めながら、目で追う書の推敲の時間である。
それは書き直すためだとか、そういうものではなく、どこに美が棲んでいるのか「視る」という行為によって学習をしているのである。

墨いろという
虹を追っている
ひとつの色で
すべてを
視るために
亡くなった父の愛硯をそばに置いている。それは彫刻された双頭の龍が墨池を縁どっていて、あいだに秘色(ひそく)の石が一粒、硯の黒い景色の中で宝石のように点いていていかにも好ましい小さな硯だった。父も母も亡くなって久しいある日、棲むひともない家を処分しなければならなくなった。
ポツンと父の文机に置かれてあったこの硯を丁寧に、丁寧に洗い呼吸させた。
硯がほっと息をするようだった。水を数滴注ぎ入れ、父の使いかけの墨を磨ると墨の香りと共に父の笑顔が見えるようだった。
墨、硯、紙、筆を文房四宝という、多分わたしはこれら自然から生れた賜物に囲まれた暮らしが好きなのである。そしてここから世界を自分を覗いて見たいのだと思う。

棲む人無き
椿咲く家に
電話してみる
父と母が
出ないかと
父が亡くなり、一年半後に母が亡くなり。空っぽになった家が緑に包まれたままぽつんと残った。電話はその後、10数年そのままにしていたのでかけることができた。しかし、誰も出ない家であった。母が好んで植えていた椿はその後も、散っては咲き、散っては咲いていた。



2013.5.23